- 常に最新の在庫評価が重要
- 自動計算と内部統制が鍵
- 原理理解で実務改善実現
本記事では、近年企業の原価管理や棚卸資産評価において注目される「移動平均法」について、20代の若手ビジネスマンの皆様に向け、実務に活用できる知識と具体的な計算例を交えながら、その基本概念やメリット・デメリット、そして他の評価方法との違いについて専門的かつ分かりやすく解説いたします。
移動平均法は、商品の仕入れや在庫管理が頻繁に行われる業界において、常に最新の原価を算出できるという優れた特徴があり、経営判断や戦略策定において非常に有用な手法とされています。本稿では、2025年の最新の市場動向も踏まえ、移動平均法を理解することで、より正確なコスト分析と利益計算が実現できる理由を明らかにします。
移動平均法とは

移動平均法とは、商品や原材料の仕入れが都度行われる際に、その都度在庫の単価を更新し、常に最新の平均単価を算出する原価計算手法です。
具体的には、ある時点での在庫金額に対して新たに仕入れた商品の取得原価を加え、その数量も合算して再度平均単価を計算するという方法です。
この計算方法により、在庫の評価額は仕入れ時点の変動に柔軟に対応し、時価に近い形で反映されるため、経営者はリアルタイムで正確な利益水準や売上原価を確認できます。
また、移動平均法は、単一の平均単価で販売時の原価が決まるため、価格変動の激しい市場環境においても、価格のブレを平準化し、比較的安定したデータを提供するメリットがあります。
移動平均法の計算方法と実務上の適用例

移動平均法の基本的な計算式は以下のとおりです。
平均単価 = (期首在庫の取得原価 + 当期仕入原価) ÷ (期首在庫数量 + 当期仕入数量)
この式は、在庫に付随する金額と数量を合算し、都度平均化することで算出されます。
実務においては、例えば月初に在庫が100個、仕入れ時の単価が100円であったとすると、最初の在庫評価額は10,000円となります。
その後、仕入れが行われ、新たに50個を単価130円で仕入れたと仮定すると、計算のタイミングで次のような計算手順が踏まれます。
(10,000円 + 6,500円) ÷ (100個 + 50個) = 16,500円 ÷ 150個 = 110円
この例では、仕入れ後の在庫平均単価が110円となり、その後の売上原価の基準となります。
また、移動平均法は商品有高帳と呼ばれる補助簿に記録され、取引日ごとの在庫数量と評価額を正確に把握するために大いに役立っています。
企業では、移動平均法を採用することで、期中の在庫評価も行えるため、四半期決算や月次決算の際に、より最新の経営情報を提供できるという点が評価されています。
移動平均法のメリット・デメリット

移動平均法を用いる際の大きなメリットの一つは、常に最新の在庫評価を可能とする点にあります。
具体的には、品目ごとの仕入れ単価が変動しても、そのたびに平均単価が再計算されるため、経営判断に必要な原価情報が正確に反映されます。
特に、原材料や商品の仕入れが頻繁に行われる業界においては、移動平均法は非常に効果的な評価方法となります。
また、一度算出された平均単価を基にして、以降の売上原価の計算が行われるため、計算処理の統一性が保たれ、経理担当者にとっても作業負担の軽減が期待できます。
しかし一方で、移動平均法にはいくつかのデメリットも存在します。
第一に、仕入れごとに頻繁な計算を行う必要があるため、取引量が多い企業では、計算の手間が増加し、人的リソースやシステムの運用負担が大きくなる可能性があります。
第二に、一度算出された平均単価に誤りがある場合、後続の在庫評価全体にその影響が連鎖的に及ぶため、初期の入力ミスや計算ミスのリスク管理が重要となります。
これらの点から、移動平均法の導入を検討する際は、システムの自動計算機能や内部統制の充実が求められると言えるでしょう。
他の原価評価方法との比較
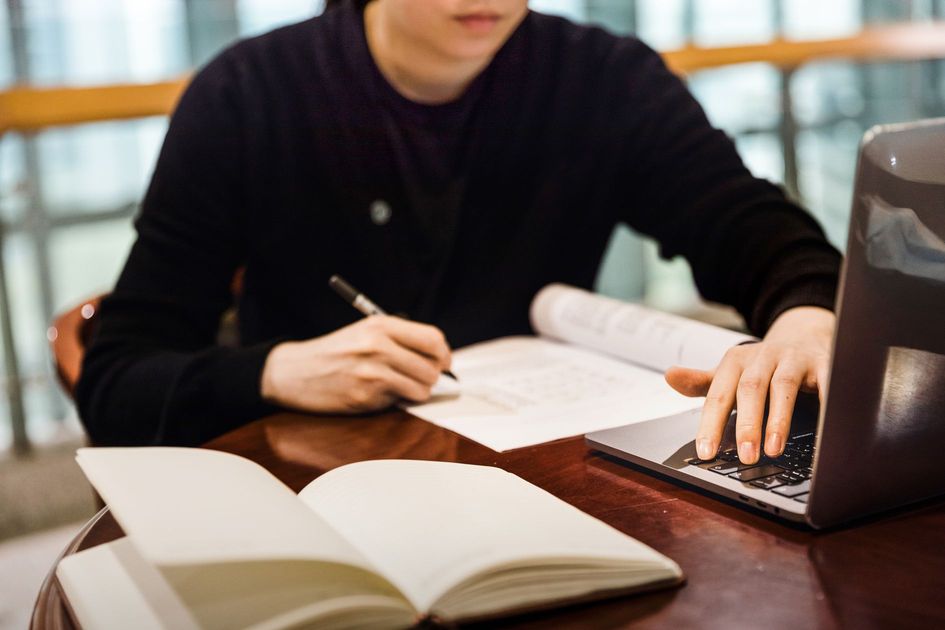
移動平均法は、同じく平均原価法に分類される手法であり、他には総平均法や先入先出法(FIFO)、後入先出法(LIFO)などが存在します。
総平均法は一定期間内の全仕入れをまとめて平均化する方法であるため、計算回数自体は少ないですが、在庫評価が期末に一括して行われるため、期間中の原価変動に柔軟に対応することが難しい場合があります。
一方、先入先出法は、最初に仕入れた商品の単価を基に売上原価を計算するため、実際の物理的な在庫の流れに近い反映が可能です。しかし、価格変動が激しい状況においては、最新の市場価格を反映できないこともあり得ます。
移動平均法は、これらの手法と比較すると、仕入れごとに平均単価を更新するため、柔軟かつ正確な在庫評価が可能です。
ただし、先入先出法や後入先出法は、在庫の物理的流れを重視した評価方法であり、税務上のメリットが享受できる場合も存在するため、企業の業種や取引形態に応じた評価方法の選択が求められます。
また、近年はクラウド会計ソフトの進化により、移動平均法をはじめとした各種原価評価方法が自動化され、計算ミスの防止や作業効率の向上が進んでいるため、適切なシステム導入の検討が今後の経営効率化の鍵となります。
移動平均法の実務導入におけるポイント

実際に移動平均法を導入する際には、以下のようなポイントに注意する必要があります。
まず、定期的な在庫確認と正確な仕入れデータの入力が不可欠です。
取引ごとに在庫数量と取得原価が正確に記録されなければ、平均単価の計算に誤差が生じ、全体の経営判断に悪影響を及ぼす恐れがあります。
次に、計算処理の自動化が進んだクラウド会計システムを活用することで、移動平均法の煩雑な計算作業を効率化し、人的ミスを防ぐことが可能です。
さらに、内部統制や定期的な監査によって、入力ミスや計算上の問題をタイムリーに発見し、修正する運用体制の整備が推奨されます。
また、市場環境や仕入れ価格が大幅に変動する場合には、移動平均法による在庫評価がどの程度実態を反映しているか、他の評価手法との適用比較を行いながら、柔軟に運用方法を見直すことも重要です。
このように、移動平均法を的確に活用するためには、システム面だけでなく、組織としての体制強化や従業員の会計知識の向上が求められます。
まとめ

以上、本記事では移動平均法の基本的な概念、計算方法、具体的な事例、そして他の原価評価手法との比較を通じて、この手法が持つ実務上のメリットや導入時に考慮すべきポイントについて解説してきました。
移動平均法は、最新の在庫評価を可能にし、原価計算の精度向上に寄与するため、特に仕入れ価格の変動が激しい業界では有効な手法です。
しかし、頻繁な計算作業の必要性や計算ミスのリスクが伴うため、正確なデータ入力とシステム自動化、内部統制の整備が不可欠となります。
経営判断の迅速化と正確な利益算出のためには、各社が自社の取引形態や業界特性に最も適した原価計算方法を選択することが求められます。
なお、最新のクラウド会計ソフトは、移動平均法をはじめとする多様な評価方法に対応しており、効率的な経理処理を実現するための強力なツールとなっています。
20代の若手ビジネスマンの皆様におかれましては、こうした会計手法や最新のシステムの動向を理解することで、今後のキャリアや経営戦略において、正確な原価管理や財務分析を行い、より良い経営判断を下すための糧としていただければ幸いです。


