- 心の平穏維持が大切
- 危機感を持って行動
- 自己研鑽と対策が鍵
近年、企業環境や個人のキャリア形成において、心理的な要因が重要視される中で、「正常性バイアス」という概念が注目を集めています。正常性バイアスとは、予期しない事態や災害、突発的なリスクに直面した際、心の平穏を維持するために「自分は大丈夫」「これはいつもの延長線上の現象」と認識してしまう心理的メカニズムです。2025年現在、グローバルな経済環境の変化や新型ウイルス感染症など、様々なリスクが横行する中、若手ビジネスマンにとって正常性バイアスへの対策やその理解は、安心して業務に従事するための必須知識となっています。
正常性バイアスとは

正常性バイアスは、突発的かつ予期しない出来事に遭遇した際、心の平穏を保つために「通常状態である」と自らを安心させるメカニズムです。
この現象は、人が日常のルーチンや慣れ親しんだ状況に基づいて判断を下す際に、突発的な変化の可能性を軽視する傾向として現れます。
例えば、災害時において「自分は大丈夫だろう」と考え、適切な避難行動が遅れることが実際の被害拡大につながる可能性があります。
具体的な事例として、2003年の韓国・大邱地下鉄放火事件においては、乗客が煙が充満している中でも「自分は大丈夫」と判断し、避難のタイミングを逃した結果、甚大な被害が出たとされています。
また、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにおいても、マスク着用の徹底やソーシャルディスタンスの維持が必要であるにもかかわらず、「自分は感染しない」といった誤った安心感が対策の遅れを招く一因となりました。
心理学や行動経済学の領域において、正常性バイアスは多くの実験からもその存在が確認されており、実験室内で煙が発生した際に、複数人数の状況下では危険認知が遅れたというデータが示されています。
このように、正常性バイアスは本来、心の平穏を保つための有用な機能である一方、非常にリスクの高いシーンにおいては判断ミスを誘発する大きな要因となり得るのです。
正常性バイアスの注意点

正常性バイアスが及ぼす影響は、個人の行動や企業の経営において多岐に渡ります。
第一に、個人レベルではキャリア形成において自分自身や組織の潜在的な危機に対して鈍感になる傾向があります。
例えば、自らの能力やキャリアに自信が過剰になると、転職やスキルアップに必要な自己研鑽の機会を逸してしまう恐れがあります。
第二に、正常性バイアスは手順やルールの遵守を軽視させる要因となり得ます。
自分だけは例外的に大丈夫だと考えることにより、組織内で決められた手順や倫理基準を無視し、結果として業務の混乱や事故・災害を引き起こすケースが見られます。
第三に、都合の悪い情報やリスク情報に対して「見なかったことにする」心理が働くことで、適切な対策が後手に回る可能性があります。
このような心理的傾向は、個人だけでなく組織全体にも波及し、経営陣が「自社は大丈夫」と過信する結果、緊急対策の準備不足やリスク対応の遅延を招きます。
特に中小企業においては、経営環境の変化が激しい現代において「倒産の危機」を回避するためにも、常にリスクマネジメントの視点を持つことが重要です。
さらに、正常性バイアスはハラスメントや評価業務においても否定的な影響を及ぼす可能性があります。
評価者が自らの安心感から自己評価や類似性に基づいた評価を行うと、客観性を欠いた寛大化効果や厳格化効果が発生し、公平な評価ができなくなるリスクがあるのです。
また、同調性バイアスと混同されやすい点も注意が必要です。
同調性バイアスは周囲の意見や行動に合わせる心理を意味し、集団としての一致団結を促す一方で、時として個々の判断力を低下させる可能性があります。
正常性バイアスは、あくまで自らの認知・判断の先入観に基づくものであり、常に「現状維持」や「過小評価」というリスクが内在している点に問題があります。
このような注意点を踏まえ、企業や個人は日常的にリスクに対する鋭敏な感性を養い、常識にとらわれずに状況を再評価できる体制を整える必要があるのです。
正常性バイアスに対する具体的な対策

正常性バイアスの影響を最小限に抑えるためには、事前の準備と意識改革が求められます。
まず第一に、日頃からあらゆるリスクシナリオや非常事態を想定し、シミュレーションを行うことが有効です。
これにより、突発的な事態に直面した際にも冷静に対処するための下地を作ることができます。
第二に、具体的な行動指針を策定することが重要です。
行動指針は、災害や緊急時にどのようなプロセスで判断を下し、どのように行動すべきかを明文化したものです。
これにより、個々の判断に委ねられる部分を最小限に抑え、組織全体で統一した対応が可能となります。
第三に、自己反省と訓練を重ねることで、思考停止に陥らないようにする必要があります。
自らの行動や判断に対して常に疑問を持ち、過去の失敗から学ぶ姿勢が、正常性バイアスの弊害を防ぐ大きな鍵となります。
特に若手ビジネスマンにとっては、キャリアの早い段階からこうした意識を持つことが、後の大きなリスク回避能力へと直結します。
企業においては、定期的なリスクマネジメント研修やシミュレーション演習を実施し、全社員が危機意識を共有する環境を構築することが不可欠です。
さらに、評価システムにおいては、自己評価バイアスや寛大化・厳格化傾向を防止するために、複数の評価者による交差評価や客観的なデータに基づくフィードバックを取り入れる試みも行われています。
これらの対策は、正常性バイアスだけでなく、他の様々な認知バイアスがもたらすリスクを総合的に抑制するための基盤となるものです。
まとめ
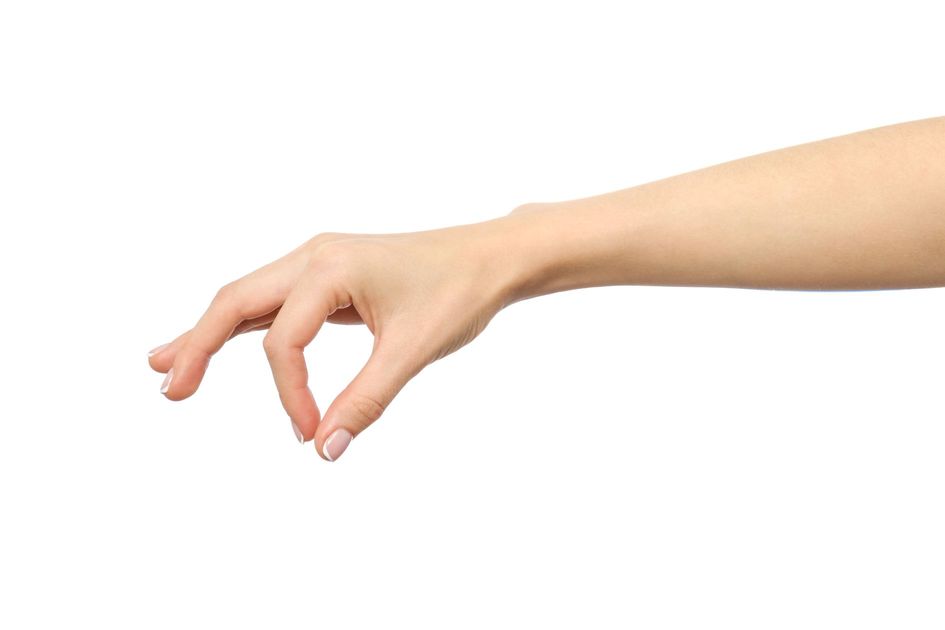
正常性バイアスは、人間が危機的な状況下でも心理的な平穏を維持しようとする自然な反応ですが、その結果、適切なリスク認知や判断が遅れる危険性をはらんでいます。
実際の災害事例や企業の経営状況からも明らかなように、正常性バイアスは個人のキャリア形成、業務プロセス、ひいては企業の存続にまで大きな影響を及ぼし得る要因です。
また、同調性バイアスやその他の認知バイアスと併発する場合、評価の公平性や意思決定の適正性が損なわれる危険性が高まります。
このため、日頃からあらゆるリスクを想定し、具体的な行動指針を策定すること、そして自己検証と継続的な訓練を通じて思考停止に陥らない環境を整えることが求められます。
今後、企業経営および個人のキャリア形成において、正常性バイアスへの深い理解と対策は、リスクマネジメントの根幹を成す重要な要素となるでしょう。
20代の若手ビジネスマンにとっては、意識高く自己の判断過程を俯瞰し、変化する環境に柔軟に対応できる能力を養うことが、今後の成長と成功の鍵となるに違いありません。
自身の判断力を常に疑い、客観的な視点からリスクを評価することで、不測の事態においても適切な対応が可能となります。
このような自己研鑽と組織的な対策の積み重ねが、最終的には健全なキャリア形成と持続的な企業成長につながるのです。



学んだことを自身の言葉でまとめること、相手に伝わりやすくする為のひと手間や工夫、根拠と理由で論理を組み立てる事が、段々自分の中に癖として落とし込まれていると感じられる。
仕事にどう活かすかも毎回考えさせられたのも、良かった。