- 棚卸資産の低価法不可欠
- 市場変動を即反映する力
- 内部統制と届出徹底管理
2025年の経済環境下において、若手ビジネスマンにとって、企業の財務状況や経営実態を正確に把握する手段として棚卸資産評価の知識は不可欠です。
その中でも、低価法は従来の原価法と比較して、販売時の実勢や市場変動をより反映した評価方法として注目されています。
本稿では、棚卸資産の基本概念から始まり、低価法の定義、その特性、原価法との違い、メリット・デメリット、さらには実務上の会計処理や届出の注意点に至るまで、専門的かつ実務的な視点で解説を行います。
理論と実践の両側面を踏まえ、これから経営や財務に携わる若手ビジネスマンが、どのように棚卸資産評価を経営判断に活かし、適切なリスク管理や節税対策を講じるべきかを理解するための一助となることを目指します。
低価法とは

低価法は棚卸資産評価の一手法であり、企業が保有する在庫の評価において、取得原価と期末時点の時価(正味売却可能価額または再調達原価)を比較し、いずれか低い方の金額を評価額とする方法です。
この手法は、特に市場の価格変動に敏感な商品、例えば衣料品や電化製品などに適用され、原価法だけでは実態が十分に反映されない場合に有効であるとされています。
棚卸資産とは一般に、販売目的で仕入れた商品、原材料、半製品・仕掛品、完成品、さらには消耗品など、企業の業務運営において必要不可欠な在庫全般を指します。
企業の利益算出にあたっては、費用収益対応の原則に基づき、実際に販売に至っていない在庫の仕入原価を費用として認識しない必要があります。
低価法は、こうした在庫が実際の販売価格下落のリスクを抱える場合、期末評価時にそのリスクを即時に反映する手法といえ、経営実態や収益状況をより正確に捉えるための重要な施策となります。
また、低価法は原価法に比べ、在庫の損失が発生した段階で即座にその影響を計上できるため、財務諸表上の利益調整や税務上の効果といった側面でも注目されています。
企業会計基準委員会が推奨するように、減損会計や収益性の低下を迅速に認識する観点から、低価法の採用は時代の流れに合致しているとも評価されており、経営実態の適正な把握と透明性の確保に寄与する手法です。
低価法の注意点

低価法の導入や運用にあたっては、いくつかの重要な注意事項があります。
まず第一に、低価法では、原価法による在庫評価額と同時に、期末の時価(正味売却可能価額または再調達原価)の把握が必要です。
このため、市場の動向の変化や商品の特性、在庫の種類ごとに適切な時価の算定基準を設定し、関連資料(注文書、レシート、契約書等)の保存を徹底することが求められます。
また、低価法による評価は計算の手間が大きいため、計算過程における誤差や管理上の混乱を避けるために、内部統制の強化と会計システムの整備が必要不可欠です。
具体的には、原価法での棚卸資産評価を基礎として、期末時点での市場状況を反映した再評価作業が発生するため、帳簿管理や在庫管理システムとの連動が重要となります。
さらに、低価法を選定する場合は、税務署へ「棚卸資産の評価方法の届出」の提出が義務付けられており、一度評価方法を変更した場合には最低でも3年間はその方法を継続する必要があります。
このため、企業は現状の在庫構成や市場動向を十分に分析した上で、低価法の適用の可否を判断するとともに、将来的な経営計画や税務戦略と整合性を取ることが重要です。
また、低価法を用いる場合、評価損として計上される損失が翌期に戻入益として計上される可能性があるため、損益計算書や貸借対照表への影響を十分に考慮し、慎重な判断が求められます。
特に、実務上は「洗替法」と呼ばれる会計処理を用い、間接的に在庫の評価金額を調整する手法が一般的ですが、仕訳の複雑さから専門の会計士や税理士との連携が不可欠となります。
このように、低価法は実態に即した在庫評価を可能にする一方で、運用上の注意点や手続き上のハードルが存在するため、企業はリスク管理と内部統制の徹底を図るとともに、適切な情報管理体制の整備を進める必要があります。
さらに、低価法の適用に際しては、評価方法の届出が行われていない場合、自動的に最終仕入原価法が適用されるため、届出手続きの漏れが経営への影響を及ぼすリスクにも注意する必要があります。
現代のグローバル市場においては、在庫評価の正確性が国際会計基準との整合性としても求められるため、低価法をはじめとする在庫評価手法に関する知識は、今後の経営判断に大きな意味を持つといえるでしょう。
まとめ
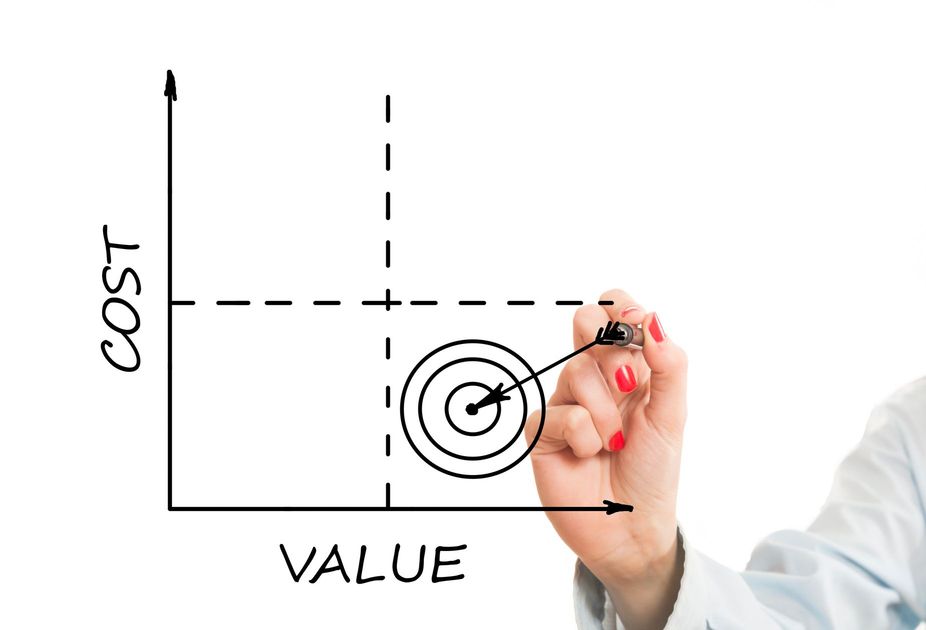
棚卸資産評価において低価法は、企業の在庫の評価をより実情に即して行うための有効な手段として位置付けられています。
取得原価と時価とのうち低い方を適用することで、販売価格の下落や市場変動によるリスクを早期に反映し、経営実態の正確な把握と迅速な損失認識、さらには節税効果の実現が期待されます。
一方で、低価法の運用には、計算の手間、内部統制の強化、十分な市場情報の取得と保存、そして税務署への届出といった注意点が存在します。
特に、実務上の仕訳処理においては「洗替法」を採用し、評価損の計上と翌期の戻入益処理という複雑なプロセスを正確に実践する必要があります。
また、一度評価方法を変更すると、最低3年間は継続して適用しなければならない点も企業にとっての重要な制約条件となります。
このことは、若手ビジネスマンが財務諸表の読み解きや企業分析を行う際に、単なる理論だけでなく、実務上の留意点や制度上の制約を理解する必要があることを示しています。
今後、さらなる国際会計基準との整合性や内部統制の厳格化が求められる中で、低価法の正確な運用は企業の経営基盤を支える重要な要素となります。
経営判断および財務戦略の策定に資するため、低価法と原価法の違い、各手法のメリット・デメリットを十分に理解し、適切な在庫評価の手法を選択することが、企業の持続的な成長や安定経営に直結するといえるでしょう。
若手ビジネスマンとしては、これらの知識を実務に応用することで、財務分析力を高めるとともに、今後のキャリア形成において、より戦略的な経営判断に寄与するスキルを養うことが期待されます。


