- 自己成長意識を忘れずに
- 具体策で不安を乗り越える
- 仲間との支えと運動重要
現代のビジネスパーソンにとって、日々の業務遂行やキャリアアップだけでなく、精神面の安定も重要な課題となっています。
とりわけ、20代という若手ビジネスマンは、将来への展望や社会的なプレッシャーの中で、漠然とした不安を感じやすい環境に置かれています。
2025年の現在、テクノロジーの進化やグローバル化、働き方の変革が進む中で、職場環境やライフスタイルは一層複雑化し、心の負担を増大させる要因となっています。
本記事では、精神科医によるアドバイスを参考に、「将来への漠然とした不安」がいかに普遍的な現象であるかを理解するとともに、その克服方法について具体的な指針を示します。
一見ネガティブに捉えられがちな心の状態も、正しく対処することで自己成長の一助となり得ます。
ここでは、その背景に潜む心理的要因や実践可能なセルフケアの手法、さらには現代ビジネスパーソンが意識すべきリスク管理の視点について詳述します。
将来への不安とは

「将来への不安」とは、決して特定の出来事や問題に起因するものだけでなく、日常のルーチンや将来的な展望に対する漠然とした恐れや心配感を指します。
精神科医の西多昌規教授が指摘するように、誰しもが経験するこの状態は、自己向上感の欠如、社会的貢献度の低さ、そして過重労働という三つの主要な要因が複合的に影響を及ぼして現れます。
まず、自己向上感の欠如は、現状維持に甘んじ自分自身の成長を実感できない状態を表しており、長期的なキャリア形成において重要なモチベーションの低下を招くことがあります。
次に、社会的な役割や貢献度に対して自信を失うと、自身の存在意義に疑問を感じ、将来的な不安を助長させます。
さらに、現代社会における過重労働は、身体的・精神的な疲労を引き起こし、日々の実感が希薄になる結果、自己存在の実感を失いやすくなります。
こうした現状は、単なる一過性のストレスではなく、長期にわたる心理的な負担として蓄積されるため、適切な対処が必要です。
また、新型コロナウイルスの影響により、未来予測の不確実性が増大した社会情勢も、この不安感を増幅させる一因として挙げられます。
個人が孤独を感じやすく、ヒマな時間が多い状況下で、内省が過度になりやすいという点も、漠然とした将来不安の背景に存在しています。
こうした心理状態は、決して例外的な現象ではなく、むしろ現代社会全体に共通するテーマと言えるでしょう。
将来への不安の注意点

漠然とした将来への不安に対処する上で、いくつかの注意点が存在します。
まず第一に、不安を感じること自体は自然な反応であり、必ずしも「病的な状態」ではないという点です。
精神科医は、不安を否定するべきではなく、むしろその存在を認め、自己理解を深める手段として利用することを推奨しています。
しかしながら、不安が日常生活に著しい支障をきたす場合や、自己評価を過度に低下させるような場合には、専門家によるカウンセリングや医療機関の受診が望ましい対応となります。
第二に、将来の不安を具体的な行動計画に落とし込むことが大切です。
ただただ先の見えない未来に怯えるのではなく、短期的かつ実現可能な目標を設定し、その達成を通じて自己効力感を高める戦略が効果的とされています。
例えば、一日の業務の中で達成感を得られる小さなタスクを積み重ねることや、定期的な振り返りを行い、自分自身の成長を実感できる仕組みを構築することが有用です。
第三に、社会的なつながりを維持することが不安の軽減につながります。
孤独感は不安感を増幅させる要因であり、同僚や友人、家族とのコミュニケーションを定期的に行うことは、精神的なサポートを受ける上でも重要です。
また、同じような境遇を持つ仲間と意見交換を行うことで、自分だけが不安に苛まれているわけではないという認識を得られ、心理的な負担を軽減する効果も期待できます。
第四に、運動や趣味を通じたストレス解消も推奨されます。
身体を動かすことは、精神のリフレッシュにつながるだけでなく、脳内の化学物質のバランスを整え、ネガティブな感情の制御に寄与します。
特に、過重労働による心身の疲労は、軽度の運動やリラックスする時間の確保によって改善される場合も多く、仕事とプライベートのバランスを意識することが求められます。
さらに、情報過多な現代社会においては、デジタルデバイスからの適切な情報摂取と、必要な情報の取捨選択も重要な課題です。
常に新しい情報が流入する環境では、自分自身の判断基準を持ち、過剰な情報から距離を置くことが、精神安定のために必要となります。
最後に、自己肯定感を高める習慣を養うことも忘れてはなりません。
自分自身の成功体験や過去の努力の成果を振り返り、自己評価を適切に行うことで、将来への不安感を相対化し、より前向きな視点で人生を捉えることが可能になります。
まとめ
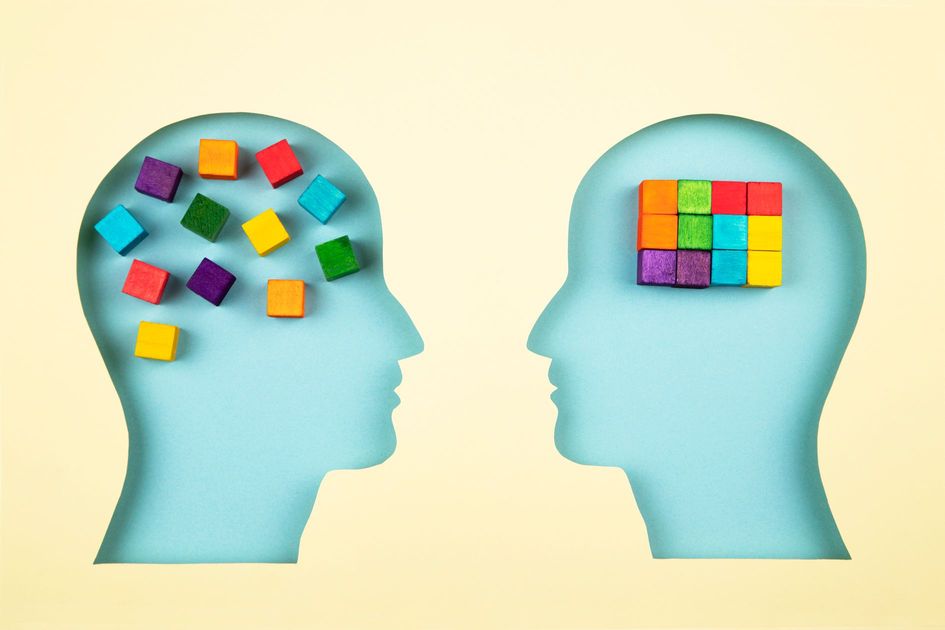
20代の若手ビジネスマンが直面する「将来への漠然とした不安」は、個人の成長やキャリア形成の過程において避けがたい現象です。
本記事では、精神科医の見解を踏まえ、自己向上感の欠如や社会的貢献度の低下、過重労働による疲労という三大要因が、この不安感を生み出す背景にあることを明らかにしました。
また、不安そのものを否定するのではなく、自己理解の一環として受け入れ、具体的な行動計画や社会的なつながり、さらには適度な運動と情報摂取の見直しを通じて、その負担を軽減することの重要性を示しました。
特に注目すべきは、ネガティブな感情に対して焦点を当てるのではなく、逆に日常の小さな成功体験や自己肯定感を高めることにより、前向きな生き方を実現するための基盤を固める点です。
現代の急速な変化や不透明な未来を前に、常に柔軟な思考と自己研鑽の姿勢を保つことは、ビジネスパーソンとしての競争力を高めるのみならず、精神的な安定にも寄与します。
最終的には、将来への不安を一つの試練として捉え、その先にある自己成長の可能性を見出すことが、充実したキャリアと豊かな人生への鍵となるでしょう。
自らのメンタルヘルスを維持するための実践的なアドバイスを活用し、日常の中で小さな変化を積み重ねながら、未来への明るい展望を築いていくことが求められます。
今後も、自分自身を適切に評価しながら、専門家の知見を参考にすることで、より充実したビジネスライフと精神的な安定を手にするための道筋が明確になるでしょう。



今までは経験に基づいたリーダーシップで自己流になっていた部分が多々ありました。本講座を受講し理論を学ぶことができたことで、今後どのようにリーダーシップを発揮していけば良いのか、目指すべきことが見えました。あとは、現場の中で経験と理論を融合させシナジー効果を発揮できるよう学んだことをアウトプットしていきたいと思えるようになりモチベーションがあがりました。
また、自社の中での自分の立ち位置しか把握できていませんでしたが、色々な業種、職種の方とディスカッションすることができ、視野が広がり、自身を俯瞰して見れるようにもなり、とても刺激的でした。
インプットは習慣化していたつもりですが、アウトプットの習慣化はできていなかったことに気づきました。どちらもできないと効果が薄れてしまうことを認識できたので、今後は、どちらも習慣化していきたいと思います。